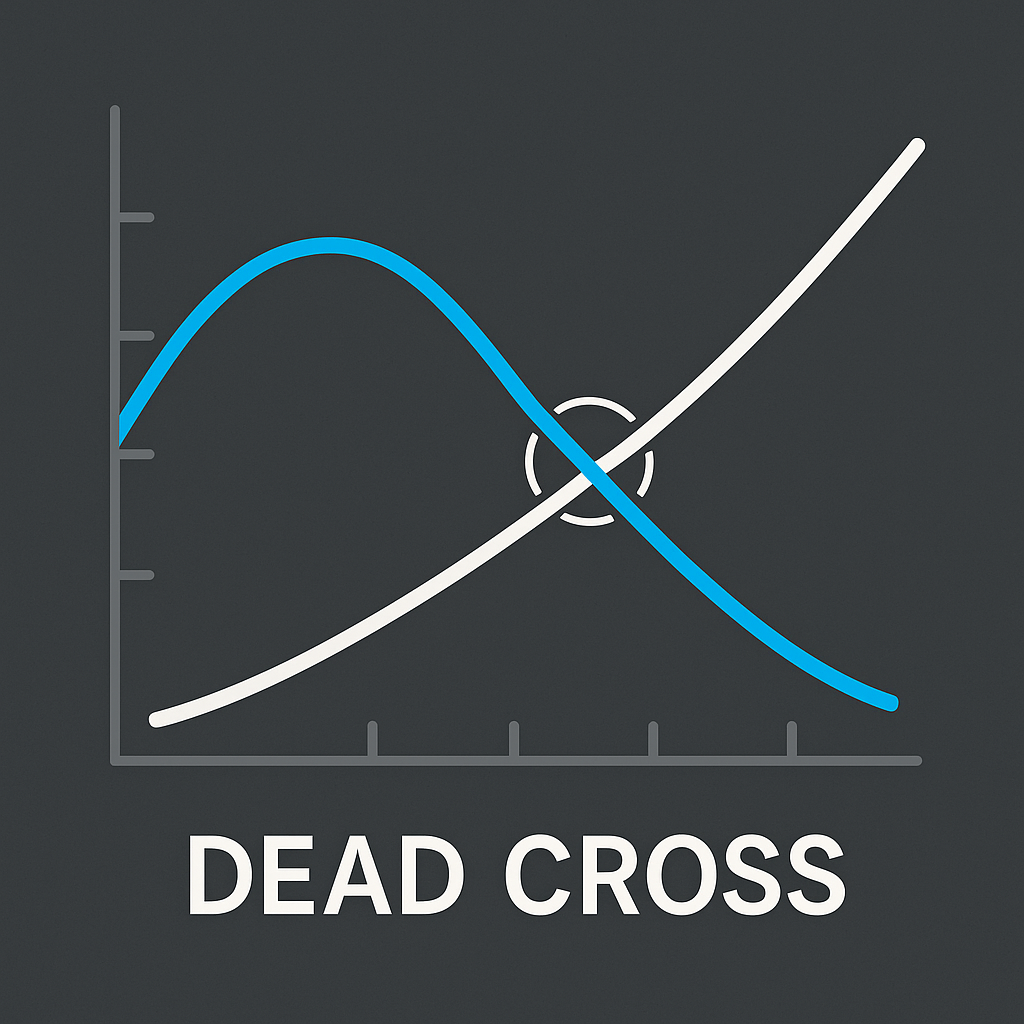「金融」とは、「金銭の融通」の略語であり、お金のやりとりを意味します。言い換えると、資金が余っている人から不足している人にお金を融通することです。広義では「お金の流れ」という意味であり、狭義ではお金の余っているところからお金の足りないところへ「お金を融通すること」、一時的な過不足を調整するためのお金の貸し借りのことを指します。
例えば、起業をしようとしている人が資金不足の場合、銀行から融資を受けたり、株式や債券を発行して投資家からお金を出してもらったりすることで資金を調達します。このような金融取引は日々膨大な量が行われており、そうした金融取引を行う場を金融市場と呼びます。
金融の重要性
金融は「経済の血液」とも呼ばれており、経済において大変重要な機能のひとつです。私たちが物を買う、企業が生産する、国や自治体が社会インフラを整備するなど、様々な場面でお金は使われますが、個人や企業、国や自治体はいつも必要なだけのお金があるとは限りません。そこで金融機関がお金の橋渡しをすることで、経済活動が円滑に行われるのです。
金融の種類
金融は形態(貸手と借手の関係)により、おおまかに直接金融と間接金融の2つに分類されます。
直接金融
「直接金融」とは、資金の貸し手と借り手が直接取引をする金融を言います1。直接金融の主な商品は、「株式」と「社債(債券)」です。株式会社や自治体が発行する株式や債券などの有価証券を、貸し手である投資家が直接購入します。
直接金融においては、投資家は企業が発行した株式や債券を一般的には証券会社を通じて買いますが、あくまで投資しているのは投資家自身です。そのため、借り手である企業が債務不履行となった場合、そのリスクはすべて貸し手である投資家が受けることになります。
間接金融
「間接金融」とは、銀行が資金の貸し手と借り手の間に入るため、借り手の企業と、資金の貸し手である預金者とは、直接的な関係がない金融のことです1。間接金融の主な商品は、「預金」と「融資」です。
銀行は預けられている「預金」を、資金を必要とする企業や個人に対して「融資」として貸し出します1。そして、預金者には利息と元本を支払い、貸し手からは元金の支払いと利息を受け取ります1。間接金融では、万一リスクがあっても銀行が負担するため、貸し手は負担する必要がありません。
間接金融のメリットとして、貸したお金が返ってこない場合のリスクは銀行が負うので、銀行が破綻しない限り預金者の預金は守られます。一方、直接金融では、お金が返ってこない場合のリスクは投資した個人などが負うことになりますが、そのリスクを取る分、投資家の収益性は一般的に高くなるというメリットがあります。
金融機関とは
「金融機関」とは、金融に関する業務を行なう組織のことで、銀行をはじめ様々な金融機関が存在しています1。
日本では、日本銀行・普通銀行・信託銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合・漁業協同組合・ゆうちょ銀行・保険会社・証券会社・ノンバンクなどがあります1。この直接金融を扱う主な金融機関が「証券会社」で、貸し手(投資家)と借り手(企業)の間に入って仲介する役割を担います1。
主な金融商品
「金融商品」とは、銀行・保険会社・証券会社などで扱う商品のことを言います。主な金融商品には以下のようなものがあります:
預貯金
「預金」とは、銀行、信用金庫などの金融機関にお金を預けること、また、預けたお金のことを言います。安全性は非常に高いですが、収益性は低めです。銀行は、預金者には利息をつけ、お金を安全に保管し、預金者に便利なサービスを提供することでお金を集めています。
株式
「株式」とは、企業が有価証券を発行して一般の出資者から多額の資金を調達して会社を運営し、その会社が上げた利益を出資者に分配する仕組みです。安全性はやや低いですが、収益性は高いという特徴があります。株式によって資本金を集めて成立した会社がいわゆる株式会社です。
債券
「債券」とは、国や地方公共団体、政府関係機関、株式会社などが一般の出資者から多額の資金を借り入れる場合に発行する一種の債務証書で、その発行者に対する債権を表示した有価証券です。安全性は比較的高く、収益性も比較的高いという特徴があります。債券は、株式とは違い配当はありませんが、その代わりに利息がつきます。
投資信託
「投資信託」とは、多くの投資家から資金を集め、その資金をもとに運用の専門家が債券や株式などで運用し、その運用成果に応じて収益を分配するという金融商品です。安全性と収益性は投資対象によって異なります。
投資信託は、一般的に「販売会社」「運用会社」「管理会社」の3つがあり、経済・金融などに関する知識を身につけたそれぞれの専門家が、役割を分担して運用しています。運用がうまくいけば、預貯金以上の収益を得ることができますが、運用がうまくいかなければ元本割れすることもあります。
外国為替
「外国為替」とは、通貨が異なる国際間のお金の取引のことを言います1。外国為替の価格は、常に変動しており、為替レートと言われる価格で取引されます1。この相場の変動を利用して利益を得る、あるいは損失を防ぐために様々な取引がなされています1。
保険
保険は、火災・死亡など偶然に発生する事故によって生じる経済的不安に備えて、多数の者が掛け金を出し合い、それを資金として事故に遭遇した者に一定金額を支払う仕組みです。
金融リテラシーの重要性
私たちは日々、お金を使っています。スマホを使うにも通信料が必要で、明日のごはんを食べるにも、漫画の更新を早めに読むにも、お金はかかります。お金を通して、私たちは社会を生きているのです。そのため、金融に関する基礎知識(金融リテラシー)を身につけることは非常に重要です。
近年では「学習指導要領」の改訂によって、2020年度の小学校から2022年度の高校の学習指導要領改訂にかけて、「金融教育」の内容が充実することになりました。現在では小学校のうちから金融教育を受ける時代になっています。
資産形成を行う上で知っておきたいことは、「家計管理とライフプランニング」、「主な金融商品」、「長期・積立・分散投資」の考え方です。お金の勉強をする際には、まずは基本となるライフプランニングや資金計画、社会保険、公的年金、税金を押さえ、その後保険や金融資産運用について学んでいくのがおすすめです。
老後資金シミュレーター
あなたの情報を入力して、老後に必要な資金を計算しましょう。
退職時の貯蓄総額
¥0
老後の総支出見込み
¥0
年金総受給額見込み
¥0
不足額
¥0
シミュレーション結果の解説
退職時の貯蓄総額: 現在の貯蓄と毎月の積立が選択した投資スタイルで運用された場合の退職時点での総額です。
老後の総支出見込み: 退職後から想定寿命までの期間における生活費の総額です。現在の年収の約70%を老後の年間支出と仮定しています。
年金総受給額見込み: 年金受給開始年齢から想定寿命までの期間に受け取る年金の総額です。
不足額: 老後の総支出から、退職時の貯蓄総額と年金総受給額を差し引いた金額です。マイナスの場合は資金不足を意味します。
改善のためのアドバイス
※このシミュレーションは一般的な前提に基づいた概算です。実際の状況は物価上昇率、投資リターン、税制改正などにより変動します。
※より正確な老後資金計画のためには、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。