日本では様々な金融機関や民間企業が資産運用サービスを提供しています。投資初心者から上級者まで幅広いニーズに対応する多様なサービスが展開されています。
本記事では、銀行や証券会社などが提供する資産運用サービスを網羅的にご紹介します。
資産運用サービス別でみた利用メリット・デメリット分析
証券会社の資産運用サービス
証券会社は伝統的に資産運用の中心的な役割を担っており、多様なサービスを提供しています。
メリット
証券会社の資産運用サービスでは、国内上場株式、REIT、ETF・ETNなど幅広い商品を取り扱っており、投資の選択肢が多様です。条件を満たせば売買手数料0円のサービスもあります。
法人の場合は、投資関連費用を必要経費として計上でき法人税の節税になる点、赤字を最長10年繰り越せる点、所得種類に区分がないため損益通算が容易な点が挙げられます。さらに、専門知識がなくても利用できる「おまかせ資産運用サービス」なども充実しています。
デメリット
証券会社での投資は元本保証がないため、投資失敗により元本割れが起こりうるリスクがあります。また、変動幅の大きい商品も多く、手数料負けする可能性もあります。法人の場合は個人よりも税率が高く(約22~35%vs個人の20.315%)、NISA口座が開設できない制約があります。
また、法人は特定口座を開設できないため、すべての収益を自分で集計・計算し確定申告する必要があります。銀行と比較すると商品数は多いものの、初心者には選択肢が多すぎて迷うこともあるでしょう。
ロボアドバイザーサービス
ロボアドバイザーとは、AIやアルゴリズムを活用して利用者に最適な資産運用を提案・実行する自動化サービスです。いくつかの簡単な質問に答えるだけで、あなたに合った金融商品を提案してくれるサービスで、「ロボアド」と省略して呼ばれることもあります。
ロボアドバイザーの種類
ロボアドバイザーには大きく分けて2種類あります。
- 投資一任型:投資商品やポートフォリオの提案に加え、実際の運用まで完全におまかせできるタイプです。最低投資金額は比較的高めで、投資信託・ETFの信託報酬以外にサービス利用料がかかります。
- アドバイス型(助言型):基本的に投資商品やポートフォリオの提案のみで、運用は自分で行うタイプです。最低投資金額は安めで、投資信託・ETFの信託報酬のみのコストとなります。無料で利用できることが多く、NISAの利用が可能なサービスもあります。
ロボアドバイザーは、投資初心者や投資に時間をかけたくない人にとって便利なサービスとして、日本でも2015年頃から普及し始め、現在では多くの銀行や証券会社で提供されています。
メリット
ロボアドバイザーは自分の運用スタイルや目的に合った商品を提案してくれる点が最大の魅力です。少額から資産運用を始められる点も初心者に適しています。
感情に左右されない合理的な判断が可能で、投資において人間が陥りやすい「狼狽売り」などの感情的な取引リスクを減らすことができます。また、低コストで運用ができる点も大きな特徴です。投資専門家に相談するための時間や手数料を抑えることができ、すべての利用者に平等に提案をしてくれます。
自動化機能により、ユーザーは商品選択や運用、リバランスに関与することなく、簡単かつ効率的に投資を行うことができます。AIは、ユーザーの投資目標やリスク許容度に基づいて最適な投資機会を見つけ、定期的にポートフォリオをリバランスします。
株式や債券など複数の投資先からAIが最適な銘柄を選び、自動的に投資バランスを調整する機能も便利です。自身でファンド選びやリバランスを行うよりも、根拠を持った投資判断ができる点も利点といえるでしょう。
デメリット
ロボアドバイザーは分散投資を前提とした運用を行うため、短期的に大きな利益は望めません。投資である以上、元本保証はなく投資成績によっては損失を被る可能性もあります。
また、一任型のロボアドバイザーは高い手数料設定のものが多く、通常の投資信託購入手数料に加えて、1%前後のロボアドバイザー利用手数料が必要になるケースもあります。
さらに、投資判断ロジックがブラックボックス化しており、「なぜこの商品を購入するのか」「なぜ儲かったのか」といった理由が分かりにくい点も留意すべきでしょう。
銀行の資産運用サービス
銀行の資産運用サービスは、銀行が顧客に提供する様々な投資や資産管理のためのサービスです。主に以下のようなサービスが含まれます。
- 預金商品:普通預金、定期預金、外貨預金など、安全性を重視した基本的な資産運用手段です。
- 投資信託の販売:国内外の株式や債券に投資する多様な投資信託を取り扱い、顧客のリスク許容度や投資目標に合わせた商品を提案します。
- 保険商品:一時払終身保険や個人年金保険など、保障機能と資産形成機能を兼ね備えた商品を提供しています。
- 債券・株式の仲介:国債や社債、株式などの売買の仲介を行います。
- プライベートバンキング:一定以上の資産を持つ富裕層向けに、より個別化された資産運用コンサルティングやサービスを提供します。
- 資産運用コンサルティング:ライフプランに基づいた資産形成のアドバイスや、退職後の資金計画など、総合的な資産運用の相談に応じます。
銀行の資産運用サービスの特徴として、安全性を重視した商品ラインナップが多い傾向があります。
ただし、銀行によって提供するサービスの範囲や特色は異なりますので、自分のニーズに合った銀行を選ぶことが重要です。また、銀行の商品は元本保証がないものも多く含まれるため、リスクとリターンのバランスを理解した上で利用することが大切です。
メリット
銀行での資産運用の最大の魅力は安心感です。多くの人が日常的に利用している銀行は、引出しや振込みだけでなく、住宅ローンや教育ローンなど人生のさまざまな場面で相談できる頼れる存在です。
インターネットバンキングを使えば、窓口より取引手数料がお得で、24時間365日いつでも利用できる便利さがあります。資産運用に興味はあるけれど商品選びに迷う人は、銀行窓口で専門家に相談できる点も大きなメリットです。選択肢が限られているため、初心者は迷いすぎることなく選択できる面もあります。
デメリット
銀行で投資できる代表的な金融商品は投資信託や外貨預金などに限られており、株式の購入はできません。商品数はネット証券と比較すると圧倒的に少なく、選択肢が狭まることは否めません。
また、銀行窓口での取引は手数料が高めに設定されていることが多く、特に外貨預金などでは為替手数料が高額になることもあります。
さらに、銀行員が提案する商品がお客様に最適とは限らず、銀行の販売ノルマなどに影響される可能性もあります。低金利時代が続いているため、預金だけでは資産が増えにくいという現実も理解しておく必要があるでしょう。
ファンドラップサービス
ファンドラップサービスとは、投資家の資産運用を専門家に任せる一種の資産運用サービスです。主な特徴は以下の通りです。
- 専門家による運用:投資の専門家(ファンドマネージャー)が、投資家の資産状況やリスク許容度、投資目標などに合わせて資産配分を決定し、運用する
- 一任型サービス:投資判断や売買のタイミングなどの決定権を投資家から運用会社に一任。投資家は日々の投資判断に関わる必要がない
- 分散投資:通常、複数の投資信託(ファンド)を組み合わせたポートフォリオで運用。リスク分散が図られます
- 定期的な見直し:市場環境の変化や投資家のニーズに応じて、定期的にポートフォリオの見直しが行われる
- 手数料体系:預かり資産の一定割合(年率)が手数料として徴収。「ラップフィー」と呼ばれ、運用手数料や取引手数料などを含んでいる
メリット
ファンドラップは、投資家の意向や運用方針に基づいて、銘柄選定や売買、ポートフォリオの管理を一任できる投資サービスです。投資経験が浅い人や運用にかける時間がない人でも、手間をかけずに投資に取り組めます。
投資信託と違い、投資家の意向を踏まえたうえで投資先の選定や売買まで全て一任できるため、より手間をかけずに運用できます。
運用中のポートフォリオの調整も行ってくれるので、自分でリバランスする必要がありません。プロの知見を活かした資産運用が可能な点も大きな魅力です。
デメリット
ファンドラップの最大のデメリットは手数料の高さです。
投資信託の運用にかかる信託報酬とは別に「成功報酬」や「固定報酬」などの手数料がかかります。通常の投資信託は信託報酬の引き下げが相次いでおり低コストで運用できるのに対し、ファンドラップは長期投資ほど運用コストの負担が大きくなります。
また、一任契約であることから運用成績の開示義務がなく、運用実績などの情報を得にくいという側面もあります。さらに、最低投資金額が高めに設定されており、まとまった資金が必要です。ただし、証券会社によっては少額から利用できるファンドラップも存在します。
NISA・iDeCo
NISAとiDeCoは、日本で利用できる税制優遇のある資産形成制度です。
- NISA:「少額投資非課税制度」の略称で、家計の安定的な資産形成を支援するための制度
- DeCo(イデコ):「個人型確定拠出年金」の略称で、2002年1月から国民年金基金連合会が実施している年金制度
メリット
NISAとiDeCoはどちらも投資の非課税制度ですが、特徴が異なります。
NISAは運用時の税制優遇があり、投資信託や株式などの売却益や配当金・分配金にかかる約20%の税金が非課税になります。一方、iDeCoは毎月の積立金額に対する全額所得控除および運用時の非課税というダブルの税制優遇があります。
長期運用では、iDeCoの「掛金全額が所得控除」になるメリットは大きく、手数料がかかっても節税効果が大きい場合があります。特に、この二つは併用することも可能で、非課税制度をフル活用した資産形成ができます。
デメリット
NISAは非課税投資枠に上限があり、制度によって年間40万円~120万円と制限されています。
また、非課税期間も5年~20年と限られています。iDeCoの最大のデメリットは、原則60歳まで資金が引き出せない点です。また、口座管理手数料(月額171円程度)がかかる点も考慮すべきでしょう。
NISAとiDeCoはどちらも非課税制度として優れていますが、運用の目的や期間、資金の必要性などを考慮して選ぶ必要があります。また、これらの制度は税制改正によって変更される可能性もあるため、最新情報の確認が重要です。
投資信託・ETF
投資信託とは、多くの投資家から集めた資金をまとめ、資産運用の専門家が国内外の株式や債券などに分散投資し、運用する金融商品です。
投資家から集めた資金を、運用の専門家(運用会社)が株式や債券などのさまざまな商品を用いて運用し、その運用成果(損益)が投資家それぞれの投資額に応じて還元・分配される仕組みになっています。
ETF(Exchange Traded Fund)は、「上場投資信託」とも呼ばれる投資信託の一種です。ETFは証券取引所に上場しており、株価指数などに代表される指標への連動を目指す投資信託です。日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)など特定の指標と連動するように運用されるパッシブ運用型のETFと、連動対象となる指標が存在しないアクティブ運用型のETFがあります。
メリット
投資信託は少額資金から手軽に始められる金融商品です。多くの投資家から集めた資金をプロが運用し、その利益を投資金額に応じて分配する仕組みで、投資信託自体が分散投資になるため初心者にも適しています。
ETF(上場投資信託)も投資信託の一種ですが、市場で株式と同様に売買でき、特定の指標に連動するように設計された商品が多いのが特徴です。ETFは投資信託より手数料が安い傾向にあります。どちらもNISA口座で購入すれば非課税で運用できるメリットもあります。
デメリット
投資信託やETFには元本保証がなく、市場の動向によっては元本割れリスクがあります。
プロが運用するとはいえ、必ずしも期待通りのリターンが得られるとは限りません。手数料面では、投資信託は購入時や解約時に手数料がかかるほか、保有期間中も信託報酬という手数料が継続的に発生します。
ETFは投資信託より手数料は安い傾向にありますが、売買時に証券会社の手数料がかかります。また、投資信託は種類が豊富すぎて選択に迷うこともあります。ETFは価格変動が大きいものもあり、市場の急変動に対するリスク管理が必要です。
外貨預金・FX
外貨預金とは、日本円ではなく米ドルやユーロなどの外国通貨で預ける預金のことです。基本的な仕組みは日本円で預金する場合と同様で、普通預金と定期預金などがあります。
FXとは「Foreign Exchange」を略した言葉で、日本語では「外国為替証拠金取引」という意味で使われています。一定の証拠金を差し入れることで証拠金以上の金額で外国為替取引ができる金融商品です。
外貨預金とFXの違い
外貨預金はシンプルに外貨を保有して金利を得る商品ですが、FXはレバレッジを活用して為替変動による差益を狙う投資商品です。外貨預金は比較的リスクが低い一方、FXはハイリスク・ハイリターンの性質を持っています。また、FXは24時間取引可能で、円高局面でも売りから入ることで利益を狙えるという特徴があります。
メリット
外貨預金とFX(外国為替証拠金取引)は、為替変動を利用した資産運用方法です。
外貨預金は日本円を外国通貨に換えて預け入れるもので、為替レート変動や金利差から利益を得られます。比較的簡単に始められ、銀行で口座開設するだけで利用可能です。FXはレバレッジをかけて取引できるため、少額資金で大きな取引が可能で、為替差益を効率的に狙えます。
24時間取引可能で、取引手数料が安いか無料の業者も多いのが特徴です。どちらも円安時には利益が出やすく、円の価値低下時の資産防衛策になりえます。
デメリット
外貨預金とFXの最大のデメリットは為替リスクです。為替レートは常に変動しており、円高になると損失が発生する可能性があります。特にFXはレバレッジをかけるため、為替変動による損失が投資額を上回るリスクもあります。
外貨預金では、銀行の為替手数料(往復で2~3%程度)が高く、短期間での売買では利益が出にくい構造です。また、現在の外貨預金金利は低水準で、かつては魅力的だった金利差によるメリットも限定的になっています。
FXは取引の仕組みが複雑で初心者には理解しづらく、短期売買を繰り返すとコストが積み重なる点も注意が必要です。
ポイント投資
メリット
ポイント投資は、クレジットカードやショッピングで貯まったポイントを使って投資できるサービスです。
三井住友カードなどでは、積立額に応じて最大3%相当のポイントが貯まるサービスも提供されています。現金を使わずに投資を始められるため、投資への心理的ハードルが低く、少額から気軽に資産運用を体験できる利点があります。
通常なら使い切れずに失効してしまうポイントを有効活用できる点も魅力です。複数のポイントを統合して利用できるサービスもあり、効率的なポイント運用が可能です。資産運用の入門として最適な方法といえるでしょう。
デメリット
ポイント投資のデメリットとしては、投資できる金額がポイント数に制限されるため、本格的な資産形成には限界がある点が挙げられます。
また、ポイントを投資に回すと、本来の商品購入などでポイントを使った場合に得られるメリットを逃すことになります。さらに、ポイント投資で利用できる投資商品が限られており、選択肢が少ない場合もあります。
投資先の商品によっては手数料がかかることもあり、少額投資では手数料負けすることもあるでしょう。投資の知識がないままポイントだからという理由で安易に投資すると、リスクを十分理解しないまま損失を被る可能性もあります。
主要証券会社の資産運用サービスおすすめ4社比較
いちよし証券

対面によるきめ細やかなコンサルティングサービスを特徴とする証券会社です。主に「店舗での取引」と「いちよしダイレクト(テレフォントレード)」の2つの取引方法を提供しています。
いちよし証券の主力サービスである「いちよしファンドラップ ドリーム・コレクション」は、お客様と証券会社の間で投資一任契約を締結し、お客様に代わって投資判断・売買の執行・資産管理などを包括的に行うサービスです。このサービスでは、5つの運用モデル(保守的、やや保守的、中庸、やや積極的、積極的)から、お客様の運用方針やリスク許容度に合ったモデルを選択できます。
また、国内上場株式、RIET、ETF・ETN、投資信託、債券、保険、NISAなど幅広い商品を取り扱っています。「いちよしメンバーズクラブ」では預かり残高状況や取引履歴・レポート等が閲覧できる専用サイトを提供しており、「いちよしファンド・プレミアムサービス」では預かり残高に応じて特典を受けられます。
| メリット | 対面でしっかりと相談しながら資産運用を進められる 店舗数が多いため、窓口で相談しやすい 不明点や疑問点をその都度解決できる 資産運用や投資に関するコラムが充実しており、投資について学びながら資産形成できる |
|---|---|
| リスク デメリット | 投資一任契約に基づく運用のため、投資元本は保証されず、元本割れのリスクがある 運用にかかる費用として、固定報酬制または実績報酬併用制の料金体系があり、投資顧問報酬と口座管理料の合計額がかかる 間接的に負担する費用として、信託報酬(信託財産の年1.15%±0.2%程度(税込))がかかる |
公式サイト:https://www.ichiyoshi.co.jp/
SBI証券

国内株式取引(条件を満たせば売買手数料0円)、投資信託、外国株式(9カ国)、IPO株など幅広い投資商品を取り扱っています。さらに、SBIラップという運用コースを自由に選べるおまかせ資産運用サービスも提供しています。
SBI証券の資産運用サービスには、「SBIラップ」という全自動の資産運用サービスがあります。これは、SBI証券とFOLIOが共同開発したサービスで、「匠の運用コース」では野村アセットマネジメントと提携して運用を行います。
また、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)サービスも提供しており、専門的な知識と豊富な経験を持つプロに相談し、自分に合ったポートフォリオを組んでもらえます。
SBI証券では、ポートフォリオマネジメントサービス(PMS)も提供しており、顧客に代わって資産運用の専門家がポートフォリオを管理します。これには「Pure Advisory Services」「Non-Discretionary Portfolio Management Services」「Discretionary Portfolio Management Service」の3種類があります。
| メリット | 金融の知識がなくても全自動で資産運用が可能 少額(1,000円単位)から積立投資を行うことができる4 IFAサービスを利用すれば、専門的な知識と豊富な経験を持つプロに相談できる 自分に合ったポートフォリオを組んでもらえる IFAコースのみ取り扱っている商品に投資できる |
|---|---|
| リスク デメリット | SBI証券は市場シェアが近年落ちている傾向がある インターネット取引が中心のため、対面サポートが限られている 高い手数料、古い取引プラットフォーム、顧客サービスの質に課題がある場合がある7 投資元本は保証されず、市場変動によるリスクがある |
公式サイト:https://www.sbisec.co.jp/
楽天証券

楽天証券の主要な資産運用サービスとして「楽ラップ」があります。これは、お客様に代わって楽天証券が投資を行うサービスで、ロボアドバイザーがたった2分でお客様に合った運用コースを無料で提案します。1万円から始められ、楽天証券に口座があれば専用口座の開設も不要で簡単に申し込めます。
楽ラップは、お客様の診断結果に基づき、お客様に代わって資産運用を自動で行うサービスです。「低コスト」で「少額」からはじめられる「本格的」なラップサービスを実現しています。
また、楽天証券は初心者向けのサービスに注力しており、投資が初めての人でも開始しやすいのが特徴です。口座開設や新規取引で楽天ポイントが付与されるなど、初心者へ向けたサービスも豊富です。
| メリット | 初心者が利用しやすい 手数料が安い(年率1%未満の低コスト) 金融商品が豊富 楽天ポイントがつく・利用できる 楽天関連のサービスと連携できる 取引ツールが充実している 投資情報が充実している |
|---|---|
| リスク デメリット | 投資元本は保証されるものではなく、元本割れのリスクがある 運用にかかる費用として、固定報酬型と成功報酬併用型があり、固定報酬型では最大で運用資産の0.715%(税込・年率)、成功報酬併用型では最大で運用資産の0.605%(税込・年率)+運用益の積み上げ額の5.50%(税込)がかかる 間接的に負担する費用として、信託報酬(最大で信託財産の0.330%(概算)(税込・年率))などがかかる |
公式サイト:https://www.rakuten-sec.co.jp/
マネックス証券

マネックス証券の主要な資産運用サービスとして「マネックスアドバイザー」があります。これは、高度な金融工学理論やマーケットの専門家によるサポートを受けながら、手軽に世界中の多様な資産に分散投資をするサービスです。運用プランは2,000以上の資産配分の組合せの中から、お客様一人ひとりの投資方針に合わせて提案されます。
また、マネックス証券は、投資一任契約に基づく裁量的および非裁量的な投資顧問サービスも提供しています。裁量的サービスでは、契約の開始時に顧客との間で締結された契約に基づいて、証券の選択と取引量を決定する権限を持ちます。
マネックス証券では、NISAやiDeCoといった税制優遇制度、国内外の株式、投資信託、ETF、FX、暗号資産CFDなど幅広い商品を取り扱っています。
| メリット | リスク管理に徹底的にこだわり、資産運用プランの作成からゴール達成まで全てサポート 毎月1万円から自動積立サービスが無料で利用可能 提案された運用プランは自由にカスタマイズ可能 初心者からベテラン投資家まで、手軽に思いどおりの資産運用ができる IPO(新規公開株)の引受け件数実績が全証券会社でトップ5 |
|---|---|
| リスク デメリット | 投資元本は保証されず、元本割れのリスクがある 運用にかかる費用がかかる 投資判断は市場環境に左右される可能性がある 一部のサービスでは最低投資額(10万ドル程度)が必要な場合がある |
公式サイト:https://www.monex.co.jp/
主要ロボアドバイザーサービスおすすめ6社比較
AIや金融アルゴリズムを活用し、自動で資産運用を行うロボアドバイザーサービスが増加しています。
WealthNavi(ウェルスナビ)

WealthNaviは全自動で資産運用を行う「投資一任型」のロボアドバイザーです。長期・積立・分散投資を基本として、6つの質問に答えるだけで最適なポートフォリオを提案してくれます。
約7〜8年間で資産が1.7〜1.8倍になった実績があり、長期運用向けの設計となっています。1万円から始められる全自動の資産運用サービスで、2016年7月のサービス開始以来、預かり資産1.4兆円、運用者数41万人と業界トップの実績があります。
| メリット | 完全自動運用 – 投資経験がなくても、資産運用を全て自動で行ってくれる アクセスの容易さ – スマホで手軽に資産運用状況を確認できる 少額投資対応 – 1万円から始められ、少額でも最適なポートフォリオを実現 税金最適化 – DeTAX機能により税金負担を自動的に軽減(特定口座のみ) NISA対応 – 一般NISAや新NISA口座での運用が可能 長期割引 – 継続利用と運用金額に応じて手数料が割引される制度がある |
|---|---|
| リスク デメリット | 比較的高い手数料 – 年率1.1%と、他社サービスと比較してやや高め 短期的な利益は期待できない – 長期運用を前提としており、短期的な利益は得られにくい 元本割れの可能性 – 資産運用である以上、市場の変動によって元本割れのリスクがある つみたてNISA非対応 – つみたてNISAは利用できない(一般NISAや新NISAには対応) 提携サービスの制限 – 「WealthNavi for」シリーズから通常のウェルスナビへの移管は原則不可 |
公式サイト:https://www.wealthnavi.com/

ROBOPRO(ロボプロ)

ROBOPROはFOLIO(SBIグループ)が提供するAI投資サービスで、40以上の指標を学習したAIが投資判断を行います。その予測に基づいて月に1度投資配分を変更。2020年1月のサービス開始から約3年で+40%以上のパフォーマンスを記録し、相場を先読みした投資戦略が特徴です。
| メリット | 高度なAI活用 – 40種類以上のマーケットデータを分析し、先行性の高いデータで市場予測 柔軟なポートフォリオ調整 – 相場予測に基づいて毎月投資配分を大胆に変更し、パフォーマンスを最大化 高い運用実績 – 金融庁発表データで過去3年間のロボアドバイザーパフォーマンス1位を獲得 完全放置型運用 – 一度設定すればほぼ手間なく自動運用が可能 自動積立機能 – 投資タイミングを考える必要がなく、定期的な積立が可能 |
|---|---|
| リスク デメリット | 高い最低投資金額 – 最低投資金額が10万円、積立も最低1万円からと、初期投資のハードルが高い 高めの手数料 – 年率1.1%(3,000万円超の部分は年率0.55%)と比較的高額 NISA非対応 – NISAに対応していないため、税制優遇が受けられない 投資判断の不透明さ – 投資家の意思が反映されにくく、AIの判断に委ねられる 元本保証なし – 投資である以上、元本割れのリスクは常に存在する |
公式サイト:https://ai.folio-sec.com/
SMBCロボアドバイザー

SMBCロボアドバイザーは三井住友銀行が提供するサービスで、5つのバランスファンドから資産運用プランに合ったものを提案します。2017年9月からサービスを開始し、初期投資は1万円から、積立は毎月1,000円から可能です。
| メリット | 資産状況の可視化 – 「金融資産の色分け」機能により、余裕資金を把握した上で投資が可能 効率的な投資配分 – 効率的フロンティア上の5つのポートフォリオを提案し、最適な資産配分を実現 自動リバランス – 日々自動的にリバランスを行うため、手間がかからない 少額から投資可能 – 初期投資1万円、積立1,000円からと低コストで始められる 目標達成の可視化 – マネープラン作成時にゴール達成確率を自動算出し、調整が可能 |
|---|---|
| リスク デメリット | 手数料コスト – 信託報酬は年1.0%未満(税込)とやや高め 元本保証なし – 投資商品である以上、元本割れのリスクがある 情報の古さ – 検索結果の情報が2018年時点のもので、最新状況は確認が必要 |
楽ラップ

楽ラップは楽天証券が提供する投資一任型のロボアドバイザーで、16個の質問に答えることで5つの運用コースから最適なものを提案します。国内外の投資信託18銘柄を投資対象とし、リスク許容度に応じた運用が可能です。
| メリット | 簡単な投資先選定 – 16の質問に答えるだけで自動的に投資先を選出 選べる手数料体系 – 固定報酬型と成功報酬併用型の2通りから選択可能 下落リスク軽減機能 – 下落ショック軽減機能(DRC)により、大幅な下落時にもリスクを抑制 透明性の高さ – 商品のリスクや手数料、運用状況、リバランスの理由などの情報が透明 少額からの分散投資 – 1万円から複数銘柄への分散投資が可能 |
|---|---|
| リスク デメリット | 信託報酬コスト – 運用コストとして信託報酬0.4915%が発生(業界平均0.36%よりやや高い) NISA非対応 – NISAで楽ラップを使えないため、税制優遇を受けられない 期待リターンの限界 – 大きなリターンは期待しにくい設計となっている アプリ対応の不足 – スマホ専用アプリがない クレカ積立非対応 – クレジットカードによる積立に対応していない |
Wealth Wing

Wealth Wing(ウェルスウイング)は、株式会社スマートプラスが運営する日本株に特化したおまかせ投資サービスです。
日本株に特化した高度な運用戦略を提供する一方で、投資リスクや手数料、投資対象の限定性などのデメリットも存在します。投資家は自身の投資目的やリスク許容度に応じて、このサービスの利用を検討する必要があります。
| メリット | 簡単な投資開始 – たった2つの質問に答えるだけで、個人に適した投資戦略を提案。口座開設申込みは最短5分で、アプリを使えばすべてオンラインで完結。 高度な運用戦略:マルチファクター投資を採用し、機関投資家レベルの高度な運用戦略を個人投資家に提供。 柔軟な戦略変更:8つの戦略ポートフォリオから選択でき、景況感に応じて戦略を変更できる。 マイル還元:運用額に応じてANAマイルが貯まります。運用開始から6ヶ月間は年率1%のマイルがプレゼント 透明性:毎週パフォーマンスを公開するなど、運用の透明性が高い。 株主優待・配当金:株主優待や配当金を受け取ることができ、株主としての実感が得られる |
|---|---|
| リスク デメリット | 投資リスク:株価の下落により損失を被る可能性がある。投資元本は保証されておらず、運用による損益はすべて投資家に帰属。 最低投資金額が高い:最低投資金額が15万円と、他のロボアドバイザーと比較して高め。 海外資産への投資不可:日本株のみに投資するため、海外資産への分散投資ができない。 手数料:運用手数料は年率0.99%(税込)。さらに月額330円(税込)の情報利用料がかかる。 限定的な投資対象:投資対象が日本株に限定されているため、グローバルな分散投資を望む投資家には適していない。 |
SBIラップ

SBIラップは、SBI証券が提供する投資信託を利用したラップアカウントサービスです。AIやプロが全自動で資産運用を行い、「AI投資コース」「匠の運用コース」など、様々な運用戦略から選べるサービスです。
| メリット | 全自動の資産運用:AIやプロに商品選定から運用まで全てを任せることができる 低コストで始められる:最低投資額が1万円と少額から始められる 手数料が割安:AI投資コース:年率0.66%(税込) 匠の運用コース:年率0.77%(税込) ポイント・マイルが貯まる:運用金額に応じてVポイントやPontaポイントが貯まる。 グローバル分散投資:AI投資コースでは8種類の資産へのグローバル分散投資を行う。匠の運用コースでは9種類の資産に投資 市場変動への対応力:AIが相場の先読みに役立つマーケットデータを分析 |
|---|---|
| リスク デメリット | 投資リスク:金利水準、株式相場、不動産相場、商品相場等の変動や為替相場変動により、基準価額が変動。投資元本は保証されておらず、元本割れのリスクがあります。 リスク許容度に合わせた運用ができない:相場に合わせて最適な資産配分に変更するアプローチを取る。 短期的な利益は見込みにくい:長期的な投資を目的としているため、数日や数ヶ月の短期間で大きな利益を出したい人には相性が合わない 信用リスク:投資対象ファンドに実質的に組み込まれた株式や債券等の発行者の倒産や信用状況等の悪化により、投資対象ファンドの基準価額が下落し、損失が生じるおそれ |
主要銀行の資産運用サービスおすすめ5行(こう)比較
銀行も預金だけでなく、多様な資産運用サービスを提供しています。
三井住友信託銀行

三井住友信託銀行の主力サービスとして「投資一任運用商品(ラップ口座)」があります。これは、お客様にふさわしい運用プランを提案し、投資一任契約を結ぶことで、運用にかかる投資判断や売買、管理などを三井住友信託銀行がお客様に代わって一括して行うサービスです。
お客様の投資に関するお考えを確認する質問にお答えいただくと、お客様の投資方針にあった「資産配分」が5コース15種類の中から選択されます。その後、三井住友信託銀行がお客様に代わって資産配分の調整や見直しを行い、定期的に報告します。
また、投資信託、外貨預金、国債、定期預金など幅広い商品ラインナップを取り揃えており、お客様の資産運用ニーズに応じた選択が可能です。
| メリット | プロのノウハウや情報力を活用した分散投資により、安定した投資効果が期待できる お客様の投資方針に合わせた資産配分を提案してもらえる 運用開始後のコース変更が無料 お申込み手数料が不要 定期的な運用報告により、運用状況を把握しやすい |
|---|---|
| リスク デメリット | 投資商品のため元本保証はなく、市場環境によっては元本割れのリスクがある 運用期間中に直接負担する費用と間接的に負担する費用がかかる 信託報酬などの各種手数料が発生する 市場の急変時には、想定以上の損失が発生する可能性がある 長期的な視点での運用が基本となるため、短期的な資金需要には向かない |
楽天銀行

楽天銀行の資産運用サービスの特徴は、楽天証券との連携による「マネーブリッジ」サービスです。このサービスに申し込むと、シームレスな資金移動で資産運用がより便利になるほか、楽天銀行の普通預金に優遇金利が適用されるという特典があります。
また、楽天銀行では定期預金や外貨預金も提供しています。定期預金は最短1週間から最長10年までの期間設定が可能で、新型定期預金では通常よりも高い金利が魅力です。外貨預金はスマホアプリから簡単に預入れができ、米ドルなら1ドルから取引可能です。
さらに、楽天証券と連携した「楽ラップ」というロボアドバイザーサービスも利用できます。これは、無料診断で16の質問に答えると、おすすめの運用コースを提案してくれるサービスです。リスクの大小で分類された9つのコースの中から、質問の回答によってロボアドバイザーが自動で選んでくれます。
| メリット | 楽天銀行と楽天証券の連携により、シームレスな資金移動が可能 マネーブリッジ申込で普通預金に優遇金利が適用される 楽天ポイントが貯まる・使える特典がある ロボアドバイザー「楽ラップ」は少額から始められ、自分に合った運用コースを提案 スマホアプリから簡単に取引ができる利便性の高さ |
|---|---|
| リスク デメリット | 投資商品は元本保証がなく、市場変動によるリスクがある 外貨預金は為替変動リスクがあり、円高になると円ベースの価値が下がる ロボアドバイザーは機械的な判断のため、急激な市場変動への対応に限界がある 運用手数料や信託報酬などのコストがかかる オンライン中心のサービスのため、対面でのきめ細かいアドバイスが限られる |
三菱UFJ信託銀行

三菱UFJ信託銀行の主要な資産運用サービスとして「MUFGファンドラップ」があります。これは個々の投資家の意向に合わせて商品のポートフォリオを自由に選べる金融商品です4。投資目的やリスク許容度に基づいて、株式や債券、不動産投資に至るまで、多様な金融商品から成るポートフォリオが構築できます。
MUFGファンドラップには「下方リスク抑制コース」と「リスク分散コース」の2つのコースがあり、投資家一人ひとりに対して金融機関の専任担当者が付き、担当者に商品選定を一任できる点が特徴です。
また、三菱UFJ銀行はウエルスナビと提携し、「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」というロボアドバイザーサービスも提供しています。このサービスでは、自動積立とリバランス機能があり、毎月一定額を自動的に投資し、長期的な資産形成を容易に進めることができます。
| メリット | 投資家の意向に合わせたポートフォリオ構築が可能 専任担当者による一任運用で、投資の知識や時間がない人でも利用しやすい 市場環境に応じた運用の見直しが適宜行われる ロボアドバイザーサービスでは手数料体系が透明(預かり資産の1%(税別)) オンラインで完結するため、忙しい社会人にも使いやすい |
|---|---|
| リスク デメリット | 投資元本は保証されず、市場変動によるリスクがある 運用手数料や信託報酬などのコストがかかる 市場環境の悪化時には運用成績が低下する可能性がある 一任運用のため、自分の判断で迅速な売買ができない 長期的な資産形成を前提としているため、短期的な資金需要には向かない |
ゆうちょ銀行
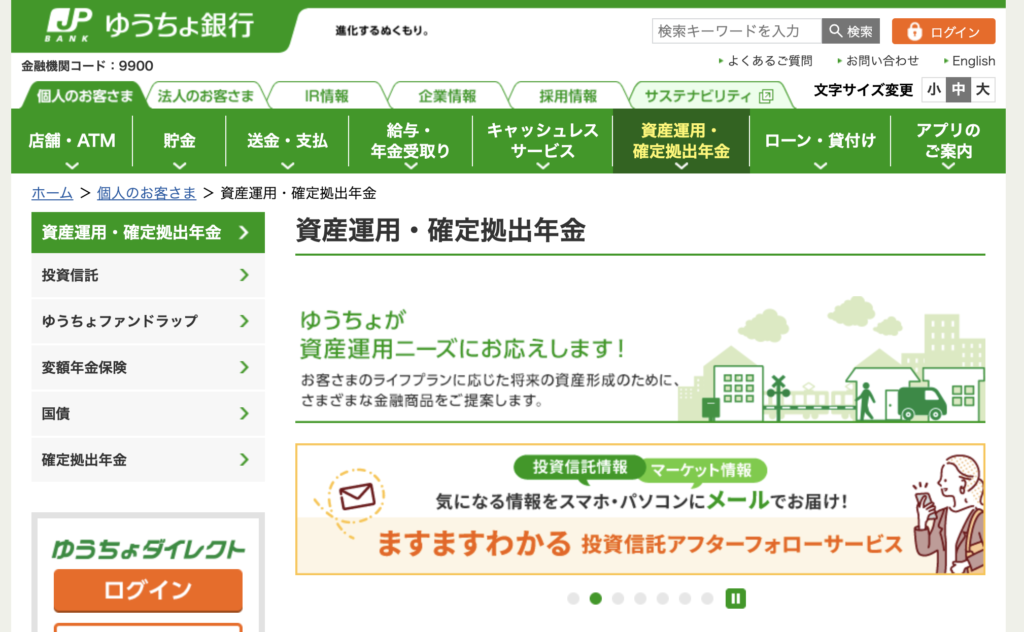
ゆうちょ銀行の資産運用サービスの特徴は、積立貯金と投資信託の提供です。積立貯金は1,000円という少額から始められ、通常貯金口座から毎月自動的に引き落とされるため、貯金の習慣がない人でも続けやすいサービスです7。
また、2023年5月からは大和証券と提携して「ゆうちょファンドラップ」の販売を開始しました。ゆうちょ銀行は193兆円の貯金残高に対し、投資信託の残高はわずか2.6兆円であり、ファンドラップの導入によって投資信託への資金シフトを促進しようとしています。
ゆうちょ銀行の積立貯金には元本割れのリスクがなく、預け入れた元本が保証されているため、相場の影響を受けることなく安心して利用できます7。また、預金保険制度の対象であるため、1,000万円までの貯金が保証されています。
| メリット | 1,000円という少額から積立貯金を始められる 通常貯金口座から自動引き落としで貯金の習慣が身につく 元本保証があり、安全性が高い 申し込みや積み立てに手数料が不要 預金保険制度により1,000万円までの貯金が保証される 全国どこでも利用しやすい店舗網がある |
|---|---|
| リスク デメリット | 金利が低く、利子でお金を貯めたい人には不向き 引き出しの自由度が高いため、ついお金を使ってしまう可能性がある インフレに対応した資産価値の保全が難しい ファンドラップなどの投資商品は元本保証がなく、市場変動リスクがある 過去に投資信託の販売時に高齢者への不適切な販売があった |
みずほ銀行

みずほ銀行の主要な資産運用サービスとして、みずほ証券が運用する「みずほファンドラップ」があります。このサービスでは、経験豊富なアドバイザーが投資家の資産状況やリスク許容度などを丁寧にヒアリングし、顧客の目標に合うように投資信託商品を組み合わせてポートフォリオを作成します。
みずほファンドラップには、「ファーストステップ」と「Mizuho Fund Wrap」の2種類があり、最低投資金額はそれぞれ500万円と1,000万円からです。運用方法や投資対象、手数料体系が異なり、顧客のニーズに合わせて選択できます。
また、市場環境の変化や顧客の状況の変化に応じて、ポートフォリオを定期的に見直し、リバランスも行います。サービス利用中は、3ヵ月に一度運用レポートを受け取ることができ、担当者に対面等で質問や相談をすることも可能です。
| メリット | プロに資産運用を任せられるため、時間と労力を節約できる 分散投資によりリスクを軽減し、長期的な安定運用を目指せる 投資家のリスク許容度や運用目標に応じて5つのコースからポートフォリオを選択可能 「相続時受取人指定特約」などの付帯サービスがあり、相続対策としても活用できる 全運用の結果が1つの運用報告書で確認でき、運用状況を一目で把握できる |
|---|---|
| リスク デメリット | 金利が低く、利子でお金を貯めたい人には不向き 引き出しの自由度が高いため、ついお金を使ってしまう可能性がある インフレに対応した資産価値の保全が難しい ファンドラップなどの投資商品は元本保証がなく、市場変動リスクがある 過去に投資信託の販売時に高齢者への不適切な販売があった |
主要ファンドラップサービスおすすめ9社比較
日本の金融市場において、投資一任型の資産運用サービスであるファンドラップは多くの金融機関で提供されています。以下の表では、国内の主要なファンドラップ運用会社について、その特徴、メリット、リスクを整理しています。
| 運用会社 | 特徴 | メリット | リスク |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | プレミア・プログラム(アクティブ運用)とバリュー・プログラム(インデックス運用)の2つを提供。最低投資額は500万円から(プレミアは1,000万円から)。手数料率1.738%。過去5年リターン0.9%。 | 初心者向けの使いやすさ、リスク許容度に合ったリターン設定、老舗証券会社の安心感。大手証券会社の信頼性と情報網を活かした運用。 | 元本割れリスク、他の商品に比べて収益性で劣る場合がある、手数料負担。最低投資金額が高い。 |
| SMBC日興証券 | 多様な金融商品を組み合わせた包括的なポートフォリオ管理サービス。最低投資額300万円から。手数料率1.32%。過去5年リターン1.1%。 | 専門家による資産運用、リスク分散、定期的なリバランス。商品ラインナップが豊富。定期的な情報提供が充実。 | 価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなど。手数料がやや高め。 |
| 大和証券 | 7つのリスク・リターン水準と約700通りの運用スタイルを提供。複数の運用口設定が可能。相続対策サポートなどの付帯サービスあり。最低投資額300万円から。手数料率1.76%。過去5年リターン1.8%。 | 目的に合わせた資産配分、安定した長期運用実績、相続・贈与対策サポート。対面でのサポートが充実。 | 元本割れリスク、契約後3ヶ月間解約不可、手数料負担。手数料が比較的高い。 |
| 楽天証券 (楽ラップ) | ロボアドバイザーが2分でコース提案。1万円から始められる。年率1%未満の低コスト運用。過去5年リターン2.0%。 | 少額からの投資可能、簡単な操作性、低コスト、ロボアドバイザーによる自動運用。楽天経済圏との連携が便利。 | 投資先の資産種類が少ない、NISA口座で運用できない、専用アプリがない、短期投資に不向き。人的サポートが少ない。 |
| マネックス証券(ON COMPASS) | 最低投資額1,000円、3ヶ月に1度の自動リバランス、年率0.66%の手数料、国内外の株式・債券・REITに投資。過去5年リターン4.6%でトップ。 | 超低額(1,000円)からの投資、グローバル分散投資、低コスト運用、自動リバランス。運用実績が優れている。 | 元本割れリスク、短期的な市場変動の影響、投資先が限定的。人的サポートの少なさ。 |
| 三井住友銀行(SMBCファンドラップ) | 長期分散投資を基本とし、厳選した14本の専用ファンドで運用。顧客ごとに最適な資産配分を提案。最低投資額500万円から。過去5年リターン1.6%。 | 長期分散投資による価格変動リスク低減、顧客ごとの最適資産配分、長期契約割引。信頼性の高さ。 | 元本割れリスク、手数料負担、長期運用が前提。SMBC日興証券の投資一任サービスであるため、銀行のサービスではない。 |
| 三菱UFJ銀行 | 「三菱UFJ資産運用プログラム」として提供。銀行窓口での対面サービス。最低投資額500万円から。過去5年リターン-2.3%。 | 大手銀行の信頼性、専門家によるサポート、リスク分散投資。保守的な運用で損失抑制を目指す。 | 元本割れリスク、比較的高い手数料、最低投資額が高め。運用パフォーマンスが低い。 |
| みずほ銀行 | 「みずほファンドラップ」を提供。専任アドバイザーによる対面相談。最低投資額500万円から。手数料率1.65%。過去5年リターン0.7%。 | 個別のニーズに合わせたカスタマイズ、定期的なリバランス、銀行の安心感。銀行との連携サービスが充実。 | 元本割れリスク、市場環境の変化による収益変動、手数料コスト。運用実績がやや物足りない。 |
| 東海東京証券 | 「東海東京ファンドラップ」を提供。地域密着型の証券会社。最低投資額300万円から。手数料率1.375%~2.75%。過去5年リターン2.8%で2位。 | 地域に根差したサービス、きめ細かいサポート、多様な運用スタイル。安定した運用実績。 | 元本割れリスク、運用実績のばらつき、最低投資額の制約。手数料がやや高め。 |
ファンドラップ利用のリスクとデメリット
ファンドラップサービスを利用する際には、以下の共通するリスクとデメリットを理解しておくことが重要です:
- 元本割れリスク:ファンドラップは預金とは異なり、元本が保証されているわけではありません。市場環境によっては投資元本を割り込む可能性があります
- 手数料の負担:投資信託の信託報酬に加えて、ファンドラップ独自の手数料(成功報酬や固定報酬)が発生します。長期投資になるほど手数料の負担が大きくなる傾向があります
- 最低投資金額の制約:多くの従来型ファンドラップでは300万円から500万円程度の最低投資金額が設定されています。ただし、ロボアドバイザー型のサービスでは1,000円や1万円といった少額から始められるものもあります
- 運用の透明性:一般的な投資信託に比べて、ファンドラップでは運用内容や保有銘柄が見えにくいことがあります
ファンドラップ選び初心者はロボアドバイザーがおすすめ
国内のファンドラップ市場では、伝統的な対面型サービスを提供する大手金融機関と、テクノロジーを活用した低コストのロボアドバイザー型サービスが共存しています。
運用実績では、マネックス証券のON COMPASSが過去5年のリターンで4.6%と最も高い成績を示しており、東海東京ファンドラップ(2.8%)、楽天証券の楽ラップ(2.0%)が続いています。一方、預かり資産額では野村證券、SMBC日興証券、大和証券といった大手証券会社が市場シェアの上位を占めています。
ファンドラップ選びにおいては、単に運用実績や手数料だけでなく、投資目的、リスク許容度、必要なサポートレベル、最低投資金額などを総合的に考慮して、自分に最適なサービスを選ぶことが重要です。特に初心者は専門家のサポートが受けられる対面型サービスを、少額から始めたい人や自動運用を希望する人はロボアドバイザー型のサービスを検討するとよいでしょう。
その他の資産運用方法
NISA・iDeCo
- NISA:少額投資非課税制度で、多くの金融機関でNISA対応の商品を取り扱っています。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):SBI証券など多くの金融機関で取り扱っています。
投資信託・ETF
- 多くの金融機関で取り扱っており、積立投資が可能なものが多いです。
外貨預金・FX
- 外貨預金:三井住友信託銀行や楽天銀行などで取り扱っています。
- FX(外国為替証拠金取引):楽天銀行や多くの証券会社で取り扱っています。
まとめ
日本では多くの金融機関や民間企業が様々なタイプの資産運用サービスを提供しています。投資初心者向けのロボアドバイザーから、専門家の知見を活かしたファンドラップサービス、さらに自分で選んで投資する従来の証券取引まで、幅広い選択肢があります。資産運用を始める際は、自分のニーズや投資スタイル、リスク許容度に合ったサービスを選ぶことが重要です。
各サービスは手数料体系や最低投資金額、運用方針が異なりますので、複数のサービスを比較検討した上で選ぶことをお勧めします。また、最近ではNISAの拡充など制度面での変更もありますので、最新情報を確認することも大切です。
- 商品・資産運用サービス – いちよし証券 https://www.ichiyoshi.co.jp/product
- ファンドラップサービスとは? | 資産運用ステップアップ編 https://www.nomura-am.co.jp/sodateru/stepup/fundwrap/
- 資産運用 | 商品・サービス一覧 – 三井住友信託銀行 https://www.smtb.jp/personal/saving
- SBIラップ サービス概要 https://go.sbisec.co.jp/prd/swrap/swrap_service.html
- おまかせ資産運用サービス – 楽天証券 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/automatic-operation-service/
- 資産運用も楽天銀行にお任せ (預金・FX等) https://www.rakuten-bank.co.jp/merit/assets/
- 資産運用サービス|クレジットカードの三井住友VISAカード https://www.smbc-card.com/mem/service/am/index.jsp
- JAバンク資産運用サービス「まかせるぞう」 https://www.jabank.org/fundwrap/
- NISA・確定拠出年金(iDeCo)・株・投資信託・債券・FX – SBI証券 https://www.sbisec.co.jp/contents/
- Simplex Personal Assets | ソリューション | シンプレクス株式会社 https://www.simplex.inc/solution/personal-assets/
- 特色ある運用コースを集結「SBIラップ」 – SBI証券 https://go.sbisec.co.jp/prd/swrap/swrap_top.html
- WealthNavi for SBI証券 サービス概要 https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=robot&dir=robot&file=home_robot_wn01.html



